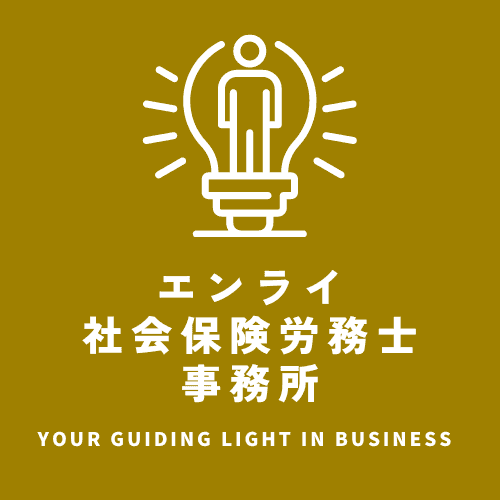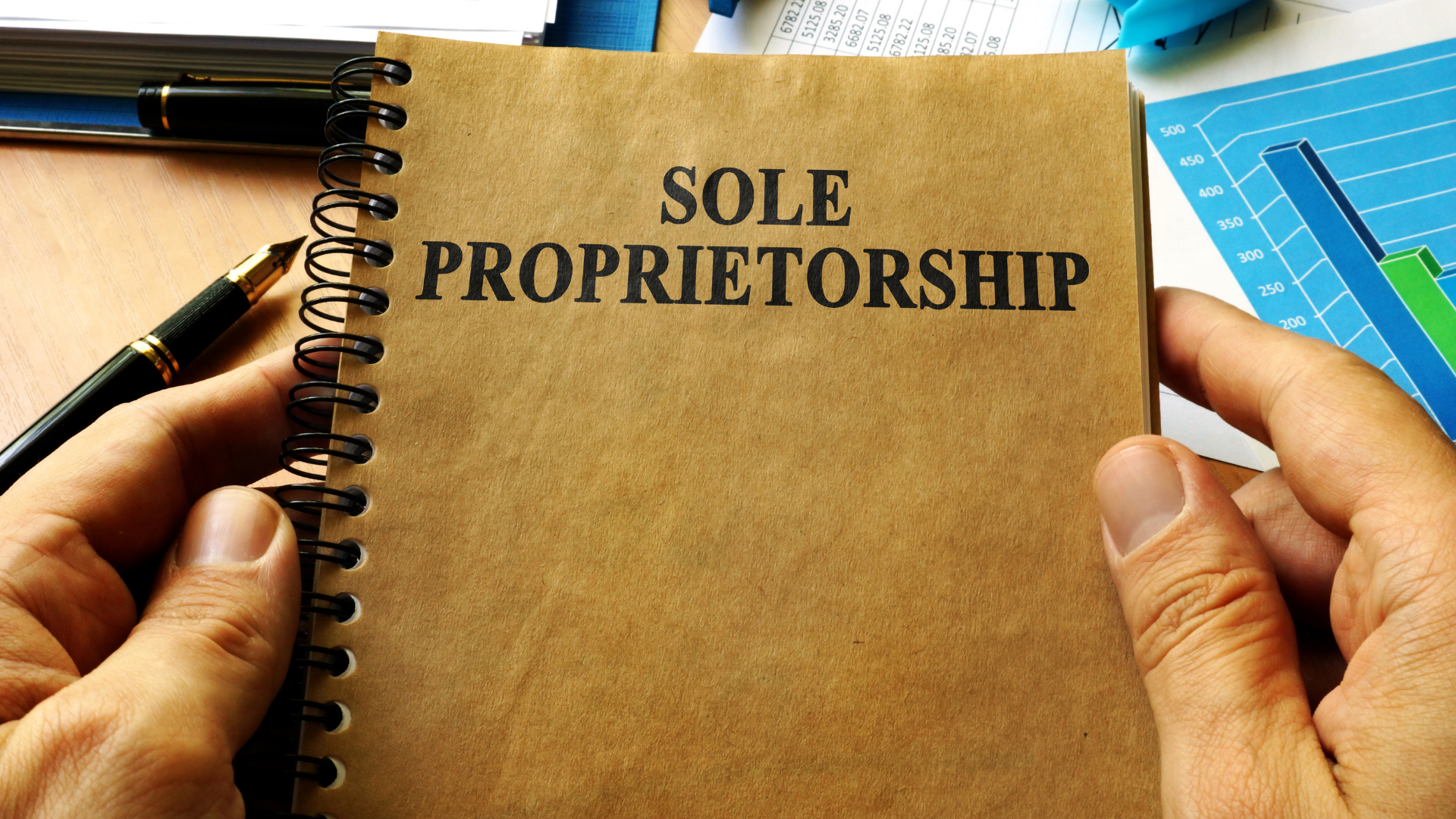
個人事業主は社会保険に入れるのか?わかりやすく解説します
個人事業主の入れる社会保険について
個人事業主は社会保険に加入することができるのか
通常、一定時間以上働いている人は、従業員でも法人の取締役でも就労者向けの社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する必要があります。
しかし、個人事業主はこれらの社会保険に加入することができません。
個人事業主の事業に従事する従業員の方は加入することができるケースはありますが、そのような場合でも個人事業主本人は加入できないので注意が必要です。
個人事業主の選択肢
健康保険の選択肢
健康保険については、市区町村で実施をしている国民健康保険に加入するか、同業者同士で実施をしている国民健康保険組合に加入するかの二択となります。
市区町村やその組合によって保険料や福利厚生などは大きく異なっているので、どちらに入るべきかというのは一概には言えません。
そのため、事業の業種などを踏まえてまずは国民健康保険組合を調査して、良い組合がなければ国民健康保険に加入するのが良いでしょう。
年金の選択肢
残念ながら加入できる年金の選択肢は1択となり、国民年金のみとなります。
国民年金は所得などに関わらず金額が固定となっており、固定額は毎年見直しが行われ、2022年度では1ヶ月16,590円となっています。
一方で厚生年金については、事業(会社)と従業員で折半をすることになっており、一定の報酬を得ている場合は、国民年金よりも割高になります。
一方で国民年金と比べて以下のメリットがあります。
- 扶養対象の配偶者は国民年金を支払う必要がなくなる
- 年金受給時に通常の年金だけでなく厚生年金を受給することができる
従業員を雇ったら社会保険手続きが必要になる場合も
ここまで個人事業主本人の方が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することができるかを見てきました。
個人事業主の方ご自身は社会保険に加入することはできないのですが、では従業員を雇ったらどうなるのでしょうか。
この場合、社会保険の加入は従業員が5人未満の場合は任意となっています。
任意ということは、入らなくても良い、ということです。
社会保険に加入をした場合、従業員と事業で負担を折半することになるため、事業への負担は多くなります。そのため任意の状況で社会保険に加入するのは、従業員への福利厚生や採用・定着を目的とする場合になるかと思います。
一方で、個人事業であっても一定の労働時間のある従業員が5人以上になった場合には、農林水産業やサービス業を除いて社会保険に加入する義務が生まれますのでご注意ください。
自分の事業の業種が該当するか、在籍する従業員が5人の中に含まれる要件を満たしているか等は、社会保険労務士に確認を取るのが確実です。
社会保険料は事業主にとって決して安い負担ではありません。しっかりと調べて必要な手続きを行なっていきましょう。
最後に
もしもお手続きに不安がある場合は、ぜひお問合せください。