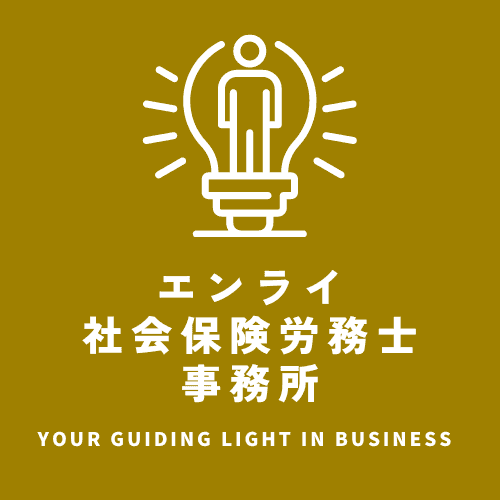初めての採用!従業員の入社に必要な手続きと目的
記事の対象範囲
この記事では、従業員を初めて採用する経営者の方向けに最低限これだけ行えばOKというような手続きについて労働法に対応する手続きと各種の行政手続きの2つに分けて解説をしていきます。
労働法に対応する手続き
労働法というと少し大袈裟に聞こえてしまいますが、労働法に対応する手続きとして必要なものはシンプルで、雇用契約書の締結です。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法では上記のように従業員に対する労働条件の明記が求められておりますが、通常は労働条件を記載した雇用契約書という形で従業員との間に締結することとなります。
条件面や退職後のトラブルなどに繋がりかねないため、雇用契約書の締結は必ず行いましょう。またその際には労働基準法で定める事項が網羅されている契約書の雛形を使う必要があることに注意してください。
なお、雇用契約書は、通常、入社日当日までには締結を行います。クラウドサインなどの電子契約での締結でも問題ないため、紙の書類の管理体制に不安がある場合には電子契約サービスを利用することをお勧めします。
またこちらは必須ではないものの従業員が残業をする可能性がある場合には、36(サブロク)協定を結んだ上で労働基準監督署に提出する必要があります。
1日8時間もしくは週に40時間を超えて勤務する可能性や法定休日に労働をさせる必要がある場合には締結するようにしましょう。1日8時間・週40時間を法定労働時間といい、これを超える時間労働させる場合には36協定の締結と届出が義務付けられています。
ただし1日数時間のパートタイマーで、上記の時間を超える可能性がないのであれば締結する必要はありません。
36協定については簡単に作ることができるページなども公開されていますので、詳しくは厚生労働省のサイトを確認ください。
各種の行政手続き
また従業員を採用した場合は、契約上の労働時間等に応じて各種の手続きが必要です。
必ず必要な手続き
従業員を採用したら必ず労災保険の手続きを行わなければいけません。
まずは事業が労災保険の対象になったことの届出となる保険関係成立届を、また労働保険は1年分の概算額を前払いする必要があるので、概算保険料申告書をそれぞれ労働基準監督署に提出しましょう。
従業員が就業中に事故などにあった場合その補償は事業主が行う必要があります。ただし労災保険に入っている場合は必要な補償は労災保険から行われることになります。
逆に言えば労災保険の手続きを適切に行なっていなければ場合によっては数千万円という補償を負担することになる可能性があるのです。
労災保険は業種によって異なりますが建設などの危険度の高い業種でなければ給与の0.3%-1%ぐらいに収まるので加入を忘れないようにしましょう。
保険関係成立届は従業員の採用から10日以内、概算保険料申告書は50日以内に提出する必要があります。
週20時間程度働く場合に必要な手続き
従業員が週に20時間以上働くような場合には、上記に加えて雇用保険への加入が必要になってきます。
まずは事業所が雇用保険の対象になったことの届出となる雇用保険適用事業所設置届と、従業員の雇用保険加入手続きである雇用保険被保険者資格取得届をそれぞれハローワークに提出しましょう。
また雇用保険料は労災保険料と併せて概算保険料申告書を提出することで前払いを行う必要がありますので、その点もご注意ください。
なお雇用保険の加入手続きを忘れてしまうと従業員が退職後に失業手当をもらおうとした際にトラブルになる可能性があるので要注意です。
いずれの手続きも入社から10日以内に行う必要があります。
週30時間程度働く場合に必要な手続き
従業員が週に30時間以上働くような場合には、上記に加えて社会保険への加入が必要になってきます。社会保険というのは健康保険と厚生年金の総称で、どちらも1つの手続きでまとめて加入することができます。
雇用保険と同様にまずは事業所が社会保険の対象になったことの届出となる健康保険・厚生年金保険 新規適用届と、従業員の社会保険加入手続きである健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届をそれぞれ年金事務所に提出しましょう。
ただし法人の場合で代表取締役が役員報酬をもらっており社会保険に加入している場合には、既に健康保険・厚生年金保険 新規適用届は不要で、従業員の加入手続きだけ行えば問題ありません。
いずれの手続きも入社から10日以内に行う必要があります。
また手続きが完了して初めて健康保険証が発行されますので、手続きが遅れると従業員の方が病院に行きづらくなりクレームなどにも繋がるので速やかに行いましょう。
最後に
さまざまな手続きが必要な上、行政手続きの期限が思ったよりもタイトで驚かれたのではないでしょうか。手続き自体は年金事務所や労働基準監督署に行けば丁寧に教えてもらうことができます。